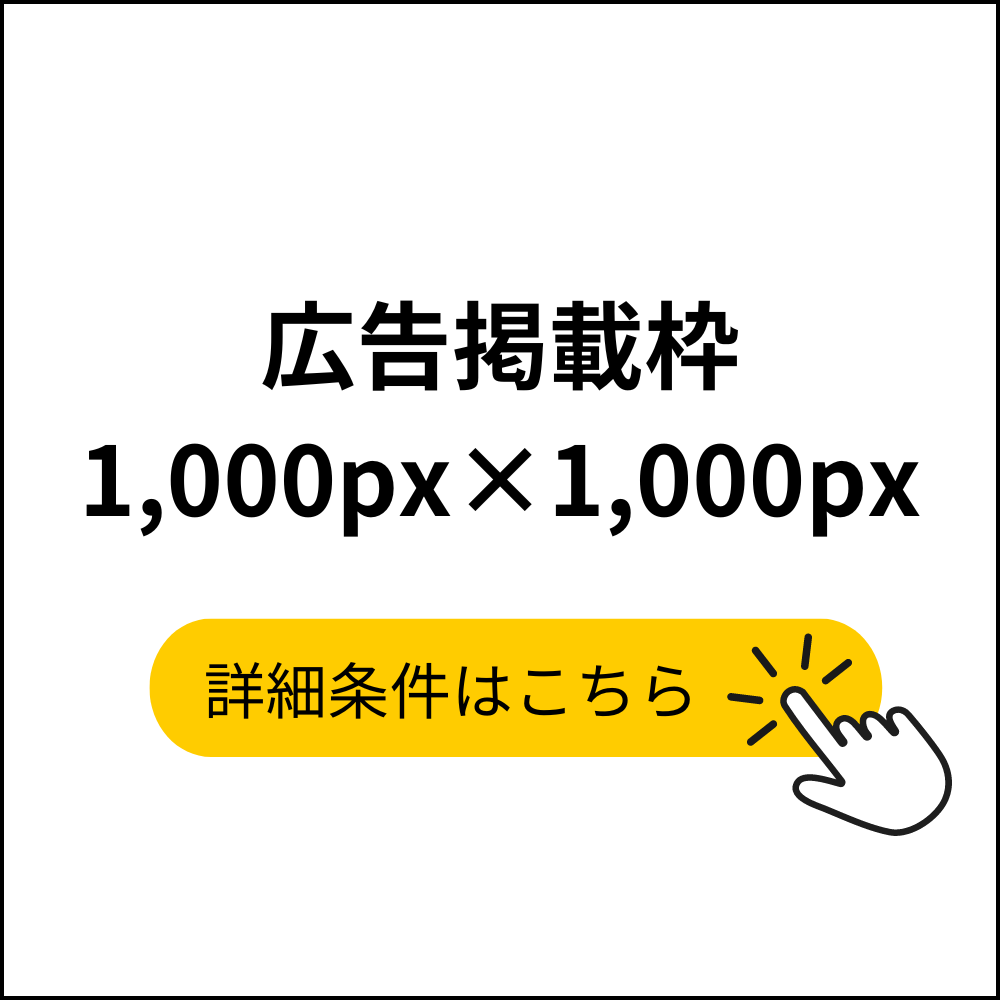予約システムの耐用年数は何年?

任せて!月額無料の予約システム「タダリザーブ」が解説するよ!
予約システムなどのソフトウェアには、会計上の耐用年数が設定されています。
予約システムを会計処理する場合は、取り扱いが難しく、会計上の考え方と税務上の考え方が大きく異なるため、自社にIT部門がない企業では、正しい会計処理ができていないケースがあります。
この記事では、予約システムの会計処理上の耐用年数と減価償却について解説します。
予約システムを導入している方は、ぜひ参考にしてみてください。
予約システムの減価償却の計算方法と減損会計について

予約システムは、制作費の資産計上と費用処理にあわせて、税務と会計で考え方が異なるため、システム稼働後の減価償却については扱いが難しい処理になります。
特にソフトウェアであっても、販売目的のソフトウェアの減価償却費と、自社で利用するソフトウェアの減損処理について注意する必要があります。
ここでは、税務上のソフトウェアの減価償却の方法と、自社で利用するソフトウェアの減価償却費・減損会計の計算方法について解説します。
税務上のソフトウェアの減価償却方法
税務上のソフトウェアの耐用年数は、ソフトウェアの利用目的によって定められています。
減価償却の方法は、毎年一定額の減価償却費を計上する定額法を用います。定額法とは、償却資産の額を法定耐用年数で割る方法です。
| 自社で利用するソフトウェア (研究開発用として利用する場合) | 3年 |
| 自社で利用するソフトウェア (販売目的として利用する場合) | 3年 |
| それ以外の用途のソフトウェア | 5年 |
となっています。
自社利用ソフトウェアの減価償却費・減損会計の計算方法
自社で利用するソフトウェアの場合、耐用年数はソフトウェアの利用可能期間となっていて、原則5年以内に設定されています。
そのため、ほとんどの企業は、税務上の耐用年数の5年で減価償却費を計上しています。
減損会計で注意すべきポイント
予約システムなどのソフトウェアを会計上で処理する場合、一番扱いが難しいのが減損会計です。
減損会計とは、投資した金額の回収が見込めないと判断された資産について、帳簿上の価値を切り下げる会計処理のことです。
これは、自社で利用するソフトウェアであっても、減損会計の対象となるとされています。
例えば、サービスを提供しているソフトウェアが、技術が進歩したことで古くなり、収益が期待できなくなった場合などが該当します。
このような処理は、会計上の基本的な考え方となっている、収益の獲得や費用の削減が確実ではない場合は費用計上すべき、という考え方に基づいて、ソフトウェアの減損処理を行う企業が多くなっています。
会計と税務の差異は税務上の加算調整
税務上では、減損損失を損金として認めてもらうことは困難です。
会計上の手続きを整備していた場合でも、減損会計を適用することでソフトウェアの現存損失を計上した場合は、税務上は親近不算入として扱い、加算調整するのが現状です。
会計と税務の考え方の違いについて

予約システムなどのソフトウェアの会計処理が難しい原因は、会計と税務で考え方が大きく違う点にあります。
会計上は、ソフトウェアを資産計上する場合、対象となるソフトウェアを利用することで、将来の利益の獲得や費用の削減が確実である、と認められることが必要です。
そのため、確実性が認められない場合は、費用として処理する必要があります。
一方税務上においては、ソフトウェアを費用として処理する場合、対象となるソフトウェアを利用することで、将来の利益の獲得や費用の削減が確実である、と認められない場合に限定されています。
そのため、確実性が認められる場合は、資産として計上する必要があります。
ソフトウェアの定義

予約システムは、一般的にはソフトウェアとして定義されますが、ソフトウェアそのものの定義について解説します。
ソフトウェアの会計基準での定義は、「ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように司令を組み合わせて表現したプログラム等をいう」とされています。
ただ、税務上の定義については、具体的な概念や範囲は、法人税本法上規定されています。
一般的には、税務上の定義は会計上の定義と同様と考えられています。
ソフトウェアの区分について

ソフトウェアの区分は、内容によって会計と税務の2つに分けられます。
ここでは、会計上の区分と税務上の区分について解説します。
会計上の区分
会計上では、ソフトウェアは「研究開発費等に係る会計基準」によって、ソフトウェアの制作目的に応じて、販売目的であるか、自社利用であるかに分類されます。
販売目的のソフトウェアは、さらに受注制作、市場販売目的に分類されます。
予約システムを導入した場合は、自社利用のソフトウェアに分類され、予約システムを販売した場合は販売目的・市場販売目的のソフトウェアに分類されます。
税務上の区分
税務上では、ソフトウェアは「研究開発用のソフトウェア」「市場販売のソフトウェア」「その他のソフトウェア」の3つに分類され、それぞれ個別に税務上の償却年数が定められています。
各分類によって、償却年数が異なるため、会計処理では異なる処理が必要です。
ソフトウェアの費用計上・資産計上

税務上においては、資産を取得するためにかかった費用については、すべて資産として計上することが原則です。
ただ、会計上では、将来の収益の獲得か費用の削減が確実かどうかで資産の計上を行うため、この両者において差異が発生する場合があります。
そのため、会計上か税務上で調整が必要です。
このソフトウェアを費用とするか資産とするかについて、市場販売のソフトウェアと自社利用のソフトウェアのケースで解説します。
市場販売のソフトウェアの場合
市場販売するソフトウェアの場合、ソフトウェアの制作費と完成後の改良・維持費用で会計処理が分かれます。
市場販売目的のソフトウェアの場合、研究開発活動とソフトウェアの制作活動の2つに区分されます。
研究開発活動が終了するまでに発生した費用は、研究開発費として、発生時に費用として処理するのが一般的です。
ソフトウェアの完成後に発生した費用については、「ソフトウェア」等の科目で無形固定資産として、資産計上されます。
ソフトウェアが完成した後に発生する費用は、2つに分類されます。
まずソフトウェアの改良など、資産価値を高めるための費用は、原則として無形固定資産として追加計上されます。
ただし、この改良の程度が大きく「著しい改良」に該当する場合は、研究開発費として発生時に費用として処理されます。
バグの修正など、ソフトウェアの価値を高めない活動にかかる費用は、メンテナンス費などにより、発生時に費用として計上します。
自社利用のソフトウェアの場合
自社利用のソフトウェアの場合は、社内業務の効率化のために利用するソフトウェアと、収益を獲得する目的で第三者に提供するソフトウェアの2つに分類されます。
どちらのソフトウェアであっても、「外部から購入する」「外部に制作を委託する」「自社で制作する」のいずれかで費用が発生します。
会計上は、自社利用のソフトウェアを資産計上するためには、対象となるソフトウェアを利用することで「将来の利益獲得または費用の削減が確実である」と認められることが必要です。
実務上では、これを立証するために、証憑を具体化しておく必要があります。
具体化の実例としては、社内稟議書,労務費を含む適正な原価管理台帳、作業完了報告書、最終テスト報告書などを整備しておき、監査や税務などの調査に耐えうる透明性を確保しておくことが必要です。
ソフトウェアを資産として計上する場合、制作費が当初の予算より多くなった場合や、バージョンアップの判断が難しい場合などで、税務処理が難しくなるケースがあります。
そのため、IT部門と経理部門が連携して会計上の処理を正しく対応できる仕組みが必要です。
まとめ

ここまで、予約システムなどのソフトウェアの耐用年数と減価償却について解説しました。
ソフトウェアの会計処理は複雑で、販売目的か自社利用かによって処理方法が異なります。
また、資産として計上するか、費用として計上するかも、ソフトウェアを利用することで利益が獲得できるか費用が削減できることが確実であるかどうかで異なります。
これらの判断は自社で行うことができず、税務署で判断されるため、あらかじめ証憑を具体化しておく必要があります。
ドライヘッドスパ専門店ヘッドミント 店舗一覧
| ヘッドミント 大須本店 | 愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル |
| ヘッドミントVIP 栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区東桜2-23-22 ホテルマイステイズB1 |
| ヘッドミントVIP 金山店 | 愛知県名古屋市中区金山1-16-11 グランド金山ビル2F |
| ヘッドミント 名駅店 | 愛知県名古屋市中村区椿町13-16 サン・オフィス名駅新幹線口206 |
| ヘッドミント 丸の内店 | 愛知県名古屋市中区錦2-8-23 キタムラビル1F |
| ヘッドミントVIP 岐阜店 | 岐阜県岐阜市神田町8-4 アートビル4F |
| ヘッドミント 静岡店 | 静岡県静岡市葵区御幸町4−2 ポワソンビル 7階 |
| ヘッドミント 新潟店 | 新潟県新潟市中央区花園1-5-3 ネットワークビル花園205 |
| ヘッドミント イオン松任店 | 石川県白山市平松町102-1 松任イオン1F |
| ヘッドミント 広島店 | 広島県広島市中区幟町12−14 幟町WINビル602 |
| ヘッドミント 池袋店 | 東京都豊島区東池袋1丁目42−14 28山京ビル202 |
| ヘッドミント 大宮西口店 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-7 AOYAMA808ビル4F |
| ヘッドミント 浦和店 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町8-2 大堀ビル202 |
| ヘッドミントVIP 蕨店 | 埼玉県蕨市塚越2-1-17TPビル201号室 |
| ヘッドミント 稲毛店 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台2-6-7 スエタケビル3階 |
| ヘッドミント 勝田台店 | 千葉県八千代市勝田台北1-3-19 新緑ビル4階 |
| ヘッドミントVIP 千葉店 | 千葉県千葉市中央区新町1-13 木村ビル |
| ヘッドミント 川崎本町店 | 神奈川県川崎市川崎区本町1-10-1 リュービマンション501 |
| ヘッドミントVIP 藤沢店 | 神奈川県藤沢市南藤沢21-9とのおかビル5F |
| ヘッドミント 京都祇園店 | 京都府京都市東山区祇園町北側270-4 Gion Hanaビル 6F |
| ヘッドミント 和歌山駅前店 | 和歌山県和歌山市美園町5-7-8 パーク美園町ビル2F |
| ヘッドミントVIP京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目11-18京橋駅前ビル2F |
| ヘッドミントVIP 東大阪店 | 大阪府東大阪市長田東2-2‐1 木村第一ビル4F |
| ヘッドミント 鹿児島アミュWE店 | 鹿児島県鹿児島市中央町1-1アミュWE通路側 |
| ヘッドミントアロマ | 愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル |
| ゼウス発毛 | 愛知県名古屋市中区大須3-26-41 堀田ビル |
ドライヘッドスパ専門店ヘッドミントのフランチャイズ募集

Lix公式オンラインショップ